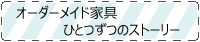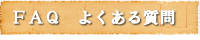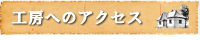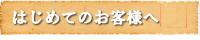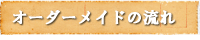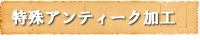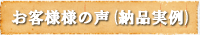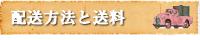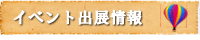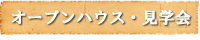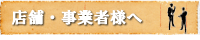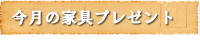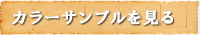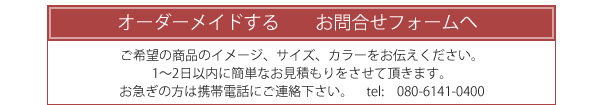レッドオークターンドレッグダイニングテーブル ろくろ脚「カントリー」 英国アンティーク調テーブル
レッドオーク無垢材を使ったターンドレッグダイニングテーブル、渋みのあるグリニッシュグレー色が絶妙に似合います。
どっしりと太いターンドレッグ(ろくろ脚)で、格調高い英国アンティーク家具をイメージしました。
クラシカルなデザイン、重厚感が満喫ください。

■商品名 : レッドオークターンドレッグダイニングテーブル ろくろ脚「カントリー」 英国アンティーク調テーブル
■サイズ : W1400〜2400 D800〜1000 H700〜750mm
※細かなサイズオーダーも可能です。
■素材 : レッドオーク材(日本産)
■塗料 : ウレタン塗料、オイルステイン等(F★★★★相当)
■送料 : ヤマト運輸らくらく家財便実費

レッドオーク無垢材を使ったアンティーク調ダイニングテーブル。
英国カントリー家具をイメージした、ターンドレッグ(ろくろ脚)テーブルです。

写真のサイズは横幅1800 奥行800 ゆったり4人がけ〜ミニマム6人がけサイズのテーブルです。
ご家庭やお店の用途に合わせてサイズオーダー対応いたします。

W1800サイズでは、細身の椅子なら6脚入れることができます。
テーブルの高さは、椅子に合わせて高さ変更対応いたします。

少し太めのろくろ足「カントリー」、どっしりした存在感が素敵。
輸入住宅や洋書スタイル、重厚感のあるインテリアづくりにおすすめです。

天板の縁にはモールディング加工が施されています。
繊細で緻密な木目がホワイトオーク材の特徴。固く丈夫で古くから高級家具の材料として人気です。

こちらは「グリニッシュグレー色」オイルステイン仕上げ、上品で落ち着いた色合い。
オイルステイン仕上げはウレタンよりも耐水性に劣りますが、ご家庭でのお手入れが容易でおすすめです。

駒止という手法で天板を固定。天板の反り割れに対応し、ゆくゆくの交換などにも便利です。
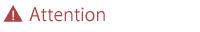
(1)こちらの商品は受注生産(オーダーメイド)となっております。ご注文をいただいてから製作を致しますので、 通常1〜2か月の製作期間を頂いております。納期のご都合がございまいたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
(2)サイズの指定が可能です。ご要望が御座いましたら、お気軽にお声掛け下さい。
(3)アンティーク加工(汚し加工)を施してあります。 色ムラ、木目が浮いている箇所もあります。届いた時からアンティーク家具の様な『落ち着いた雰囲気』を 楽しんでいただけます。 綺麗な商品をお好みの方はご遠慮下さいませ。なるべく綺麗めで、激しく傷つけて、など調整も可能です。
(4)無垢板を使っていますので、お使いのうちに木の反り・割れ・痩せ・節抜け・塗装割れなどが発生します。 お手入れにより発生を遅らせることが出来ますが、いずれは起きてくるものです。 無垢家具の特徴とご理解下さいませ。